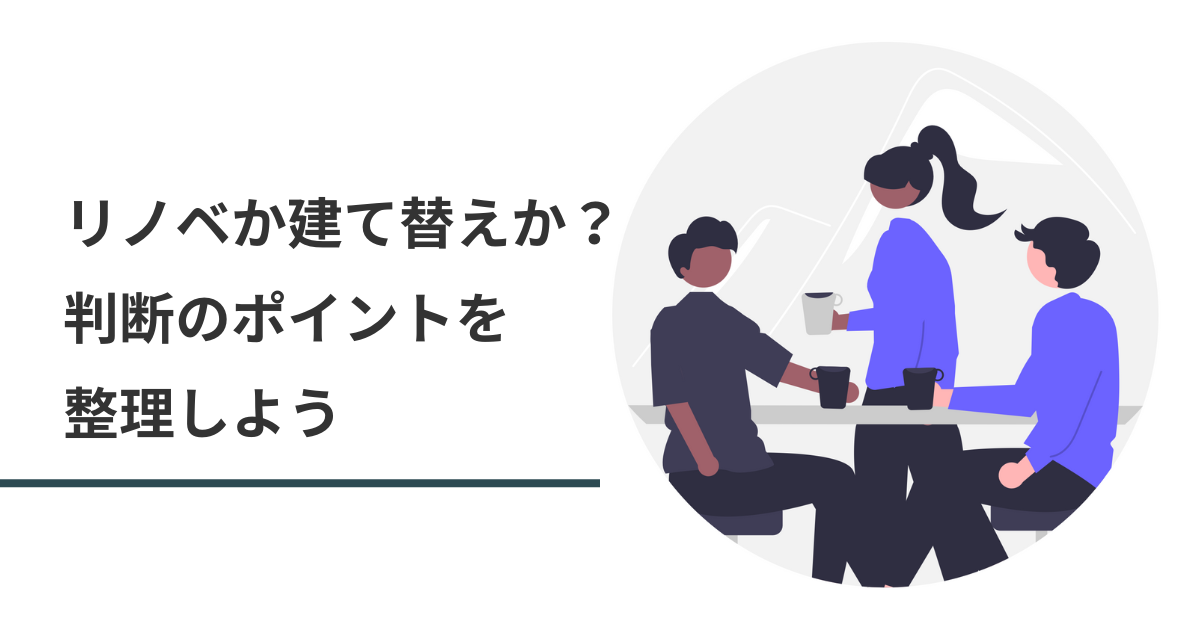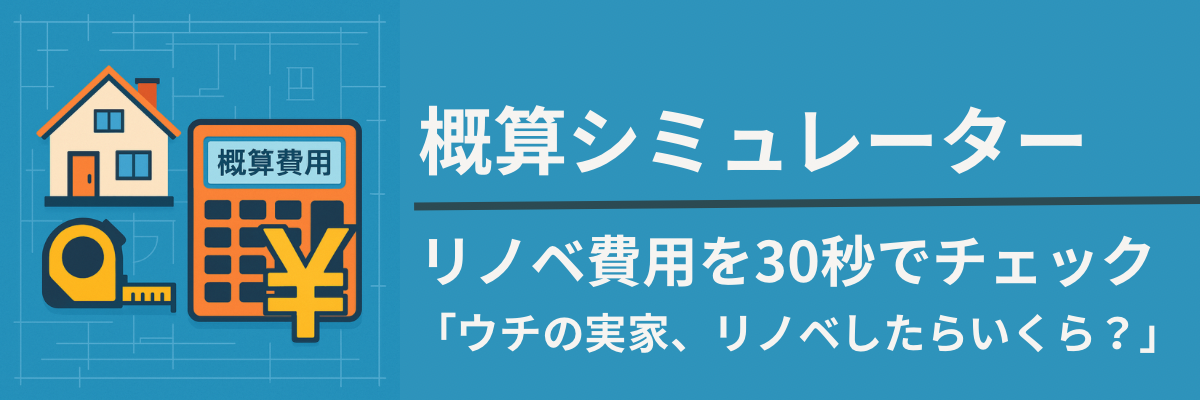🏠 リノベか建て替えか?判断のポイント
── 建築士の視点と、公的資料に基づく判断軸を整理してみました
国土交通省の「住宅市場動向調査」や、住宅金融支援機構の制度資料などをもとに、コストや制度、建物の条件から冷静に検討していきましょう。
✅【1】建て替えできる土地かどうか?
▶ 補足説明
建て替えが可能かは、土地が接道義務を満たしているかで決まります。道路に面していない、または幅が狭い土地では再建築できない可能性があります。
▶ 裏付け内容
・ 建築基準法第43条により、原則として幅4m以上の道路に2m以上接していないと再建築不可。
・ 既存建物のリフォームや一部改修は可能なことが多く、リノベでの活用が選択肢となります。
・ 不動産流通推進センター資料でも再建築不可物件の活用方法が整理されています。
✅ ポイント
→ 市役所の建築指導課や法務局で、接道義務を確認できます。
以前の建築確認申請書や敷地図が残っていれば、判断がスムーズです。
✅【2】耐震性と構造の状態
▶ 補足説明
築年数が古いだけでは判断できませんが、旧耐震基準(1981年以前)かどうかは大きな目安となります。
▶ 裏付け内容
・ 日本建築防災協会の資料によると、旧耐震住宅の多くは震度6強で倒壊リスクが高いとされ、建て替えの検討が勧められます。
・ 住宅金融支援機構の「フラット35」技術基準でも、耐震性能の確認が前提とされています。
✅ ポイント
→ 建築士による耐震診断・既存住宅状況調査(インスペクション)を依頼し、構造体の健全性を評価しましょう。
✅【3】2025年から、大規模リノベに確認申請が必要に
▶ 補足説明
2025年4月から、木造住宅でも大規模な構造改修を伴うリノベには建築確認申請が義務化されます。
▶ 裏付け内容
・ 国交省の改正概要資料によれば、主要構造部を変更するリノベは、木造2階建てでも確認申請が必須。
・ 構造図・省エネ計算・設計図書の提出が必要となり、申請費用+期間の負担が増えます。
✅ ポイント
→ 改修内容がどこまで申請対象になるかは建築士に確認を。
申請書控えがあると、対象かどうかの判断にも役立ちます。
✅【4】費用と制度の比較
▶ 補足説明
リノベの方が安いと思われがちですが、諸費用や制度の違いをふまえると単純比較はできません。
▶ 裏付け内容
・ 住宅市場動向調査(国土交通省)によると、中古+リノベの総費用は約3,000万円前後、建て替えは5,700万円台。
・ フラット35リノベ(住宅金融支援機構)では、省エネ・耐震条件を満たすと金利優遇が適用。
・ 自治体によってはリフォーム補助金もあり。
✅ ポイント
→ 自治体・金融機関・支援機構それぞれの制度をチェックし、利用可能なものを活用しましょう。
✅【5】思い入れや家族の気持ち
▶ 補足説明
法的・性能的な判断と同じくらい、「家族の思い」も大切な判断軸です。
▶ 裏付け内容
・ 専門家の現場経験では、性能的に建て替えが妥当でも「祖父母の家を残したい」「思い出を受け継ぎたい」とリノベを選ぶ例も多く見られます。
・ 国交省の調査でも「慣れた土地で暮らしたい」「親との関係を大切にしたい」といった理由でのリノベ選択が一定数確認されています。
✅ ポイント
→ どちらが合理的かだけでなく、「何を残したいか」を考えることも、納得感のある選択につながります。
📝 最後に:迷ったら、まずは“状態を知ること”から
建て替えとリノベ、どちらにも良さがあります。
そのうえで自分たちに合う選択をするには、「建物の状態」「制度の活用可能性」「家族の意志」の3点から整理していくのが大切です。
🎯 次のステップ
- ▶ 建物診断を受けたい方はこちら → 住宅診断ページ
- ▶ コスト比較の詳細はこちら → 費用比較記事
- ▶ 制度活用の基本はこちら → フラット35公式サイト