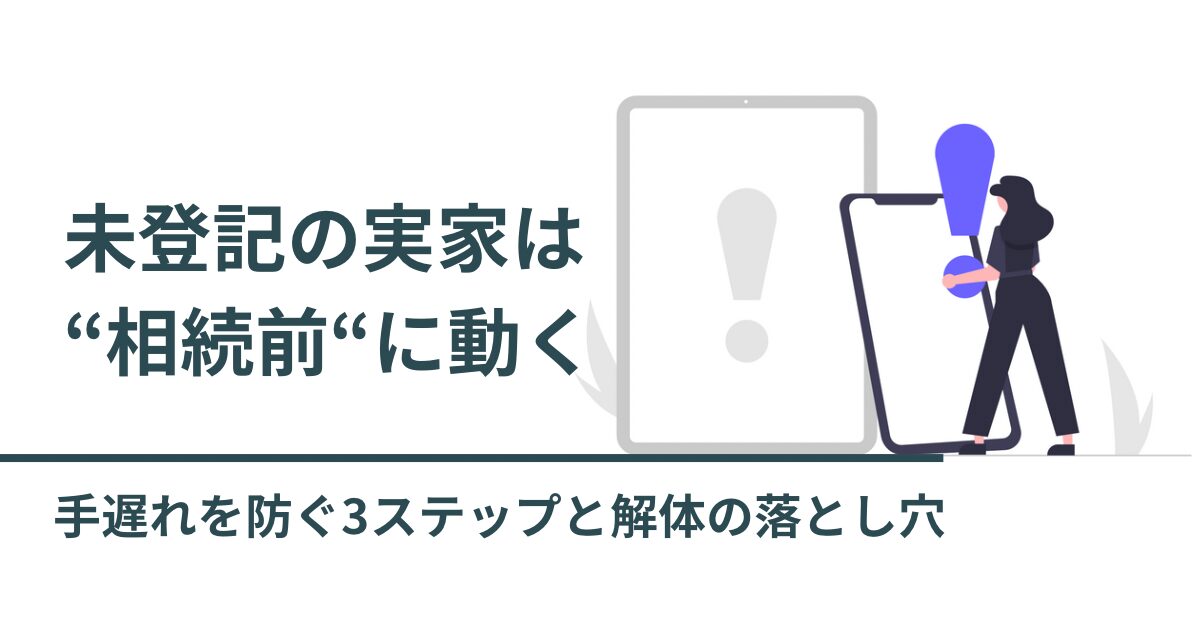未登記の実家、相続が起きてからでは間に合いません
「親が現金で家を建てたから登記していないらしい…」
そんな昔話、意外と残っています。
未登記物件は“生きているうち”に手を打たないと
解体でも売却でもすべてがストップしがち。
ここでは 放置すると何が詰まるのか と 今から取れる解決ステップ をまとめました。
ちょっと怖い話ですが、知っていれば慌てずに済みます。
未登記物件って何?
法務局に「建物表題登記」が無い状態を指します。固定資産税は課税されていても、法律上は“存在が曖昧”。登記義務(完成後1か月以内)を知らずスルーした旧来のケースが多いです。
✔ 建物表題登記 … 土地家屋調査士
✔ 所有権保存登記 … 司法書士
どうして未登記のまま放置された?
- 住宅ローンを組まない現金建築だった
- 昭和〜平成初期、申請コストや手続きの手間を惜しんだ
- 「課税されてるから大丈夫」という誤解
相続が発生すると、ここが詰まる
- 所有者不明扱いで売却・解体・融資がストップ
- 持分調整に 全相続人の実印+印鑑証明 が必須
- 2024年施行の相続登記義務化で
「取得を知った日から3年以内」or「2027/3/31」までに登記しないと過料10万円
2024‐25年:相続・所有者不明土地対策の改正要点
• 相続登記の申請義務化(不動産登記法 改正)
• 正当理由なき違反は10万円以下の過料
• 建物表題登記の未申請にも職権登記+罰則が明文化
ご存命ならまだ間に合う!“3ステップ”で未登記を解消
| STEP | やること | 専門家 |
|---|---|---|
| 1 | 固定資産税課税明細で課税床面積を確認 | 自治体 |
| 2 | 土地家屋調査士が表題登記を申請 | 調査士 |
| 3 | 司法書士が所有権保存登記 → 持分整理 | 司法書士 |
すでに相続が起きてしまったら?
1) 相続人全員の協議 → 2) 建物表題登記 → 3) 相続登記 → 4) 解体なら滅失登記。
“表題登記を後回し”にできない点に注意です。
「もう壊すしかないよね?」と思っても、ここで足踏み
① 登記簿が出せずにストップ
解体業者も役所も最初に「登記事項証明書」を求めてきます。未登記だと
「固定資産税課税明細」「現況写真」「相続人全員の同意書」など
追加書類の山。ここで数週間〜数か月コースに突入しがちです。
② 建設リサイクル法〈事前届出〉の壁
床面積80㎡以上の解体は着工7日前までに
建設リサイクル法第10条届出が必須。
添付書類に通常求められる登記事項証明書を出せない場合、
現況写真や図面で代替 → 役所との往復でさらに時間がかかります。
③ 最後に「滅失登記」で二度手間
解体完了後1か月以内に滅失登記を出す必要がありますが、
そもそも建物番号がないので表題登記 → 滅失登記の二段構え。
調査士+司法書士をワンパッケージで頼むとスムーズです。
「壊すだけでしょ?」とサクッと進めたくても、
“所有者証明 → 届出 → 二度手間登記” の三段ハードルで
テンションが一気に下がるのが未登記あるあるです。
まとめ & チェックリスト
- □ 実家の登記簿を閲覧した?(オンライン/法務局)
- □ 固定資産税課税明細と床面積が一致?
- □ 表題登記→保存登記→相続登記の流れをイメトレした?
- □ 解体予定なら「建設リサイクル法届出」の段取り確認?
- □ 土地家屋調査士・司法書士へ見積もり依頼済み?
▼ もっと詳しく調べたいときのリンク集
※リンクは 2025年7月2日時点の公開情報です。
ここまで読んで「うちもマズいかな…」と思ったら、
早めの情報整理と専門家相談がいちばんの近道です。
動き出すタイミングが早いほど、費用も手間もグッと抑えられますよ。